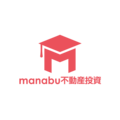売買契約は、売主と買主の「売ります」「買います」といった意思表示の合致のみで成立するのが原則ですが、不動産取引のような比較的大きな買い物をする際には、契約書の締結を行うことが通例です。ところが、売買契約や当事者の意思表示の合致だけでは、取引が成立しない場合がいくつかあります。
注意を要する不動産取引
・利益相反取引
・意思表示に問題がある場合
・契約不適合責任免責物件
これを見逃してしまうと、要件が足りないため所有権移転の登記ができないという事態になる可能性もあります。今回は、売買契約締結の他にも特別の手続きを要する取引など、特に注意を要する不動産取引についてご紹介するとともに、不動産取引の当事者である不動産投資家が、備えておくべき基本的な法的知識についても見ていきたいと思います。
特別な手続きを要する取引 その1 法人と役員との取引 【利益相反取引】
利益相反取引とは
利益相反とは当事者の一方の利益が他方の不利益になることを意味します。不動産投資においては主に資産管理法人を活用した投資を行う際に留意が必要になります。ここでは利益相反取引に該当するいくつかのパターンとその処理について紹介していきます。
<appendix>なぜ資産管理法人を活用した投資をした場合に利益相反に該当する可能性があるのか
株式会社の取締役などは、経営者として会社の営業上の秘密に通じながら、会社の業務執行を決定する立場にあります。そのような立場で、個人として、会社と相対する立場で取引を行うと、会社と取締役との間に利害の対立が生じることになります。
このような状況で取締役が個人のために行動することで会社の利益を害しないように、会社と取締役個人との取引を利益相反取引として、会社の利益を保護する制度が会社法で定められています。
パターン1 新規法人を設立し、個人所有の物件を法人に売却する行為
アパート、マンション等の不動産オーナーが、税務対策として、個人所有の不動産について、新規法人(株式会社)を設立して不動産を法人に売却し、法人所有とすることがあります。その際、不動産の所有者が代表取締役となって法人を設立する場合は、不動産オーナーである個人と、当該オーナーが取締役である会社との利益相反行為となります。
株式会社の取締役が、自分の資産である不動産について、自分個人の名義から会社名義にするために、売買契約を締結し、取締役は不動産を売って、買主である会社から売買代金を受け取ることになります。

このように会社経営者である取締役が、会社から利益を受けることは、会社と取締役との利益が相反する典型的な例になります。
このような場合には、株主総会(会社が取締役会設置会社である場合は取締役会)の承認機関の決議が必要となります。所有権移転登記をする際には、当該決議が成立したことを証するための議事録等の添付が必要となります。
パターン2 取締役個人の債務のために法人の不動産を担保にする行為

会社保有の不動産に担保権を設定する場面でも、会社と取締役の利益が相反することがあります。例えば、会社の代表取締役個人が、会社と連帯債務者となり会社所有の不動産に抵当権を設定するといったケースでは、個人の債務を担保するために会社の財産である不動産に抵当権を設定することになりますので、会社の利益が害され得る行為として、担保権の登記のために各承認機関による決議およびその議事録の添付が必要となります。
他方で、代表取締役個人と会社とが連帯債務者となって、代表取締役個人が所有する不動産に抵当権を設定する行為は、代表取締役個人が会社のために自己の財産を担保に差し出しているという状況で、少なくとも担保設定の時点では会社の利益を害することはないため、そのような承認決議は不要とされています。
合同会社と業務執行社員との取引の場合
合同会社においても、会社と業務執行社員との利益相反取引の際には、承認手続きが必要です。
合同会社は、所有と経営が一致した会社形態といわれ、会社構成員である社員が、会社のオーナーでもあり経営者でもあるという点にその特徴があります。ただし、定款により「業務執行社員」を定めることで、業務執行権を持つ社員と業務執行権を持たない社員を併存させることができます。この場合、業務執行権を持つ社員である業務執行社員が、会社経営者として株式会社の役員のような地位に就くことになります。
そして、業務執行社員が会社と売買契約の当事者として取引を行う場合は、やはり業務執行権を持つ役員が会社の利益を害するおそれのある行為をすることになりうるため、利益相反取引となります。この場合に必要となるのは、取引を行う業務執行社員以外の社員の過半数の同意です。この場合の社員には、業務執行社員はもちろん、業務を執行しない社員も含まれます。
どのような行為が利益相反に当たるのか、その肯否の考え方については、株式会社と同様です。
特別な手続きを要する取引 その2 意思表示に問題がある場合 【成年後見人制度】
例えば、不動産の所有者が高齢で認知症を患っており、明確な意思表示ができない、という場合は、そもそも売買契約などの意思表示を要する法律行為は不可能であるため、所有者本人が不動産を売却することはできません。
意思表示ができなければ、他者に行為を代理してもらうよう依頼する行為(委任契約)もできないので、不動産の所有権はそのままでは移転することができません。そういった状況でも成年後見人制度を利用することによって売買が可能になります。
認知症の親を持つ人が、親を施設に入居するための金銭を調達するため、親が一人暮らしをする実家を売却したいというケースでは成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、選任された成年後見人が、成年被後見人である本人を代理して、家庭裁判所の許可を得て、当該不動産を売却することになります。

現行の制度では、成年後見制度は一度後見人等が付されると、本人の行為能力が回復するか、本人が亡くなるまでは後見人による財産管理が必要となるため、途中でやめるということが原則としてできません。
このような硬直的な成年後見制度を、より柔軟に利用できる制度にしてほしいという要望は多く、厚生労働省の成年後見制度利用促進専門家会議では、成年後見制度の期間・範囲を限定し、制度をより柔軟に使えるようにするための検討が進められています(令和5年5月現在)。
しかしながら現状では、判断能力を欠く売主の物件を取得したいという場合は、売主に成年後見人を付してもらうのが唯一の解決策です。そのような不動産獲得は不可能ではないものの、関係者による煩雑な手続きが必要となり、時間もかかるため、注意が必要です。
取引を進めるうえで、売主側に意思表示の問題等の事態が発覚した場合は、当該取引は、売主側の判断と行動に委ねられることになります。物件を売りに出している以上、少なくとも売主側の売却の意思は高いと思われますので、売主がどうしても売却する必要があれば、成年後見人を選任し、当該後見人との取引になります。
成年後見人は、売主である成年被後見人にとって不利益な取引は行えませんし、不動産のような大きな資産を動かす場合には、家庭裁判所の許可を要することになります。売主本人の居住用不動産であっても、例えば当該物件を売ることで、被後見人に望まれる施設に入ることができるだけの金銭が得られる等の事情があれば、むしろ被後見人には利益となるため、売却可能性は高くなります。
特に魅力的な物件が取引の対象として一般消費者の前に現れるということは、何かしらの事情がある可能性も高いと考えられます。買主としては、自己の取引の対象として魅力的な物件が出てきたらまず、売主の状況を可能な限り見極める姿勢が重要です。
特別な手続きを要する取引 その3 契約不適合責任免責物件
契約不適合責任とは
契約不適合の状態というのは「引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないこと」とされ、不動産の場合はその物件を居住スペースや事務所等、それぞれの目的に応じた利用をするうえで不具合があることをいいます。
売買契約の目的物について、民法上は契約不適合が見つかった場合には、買主はそれを知った時から1年以内に、売主に対し目的物の修補や損害賠償などの責任を追及できることになっています。「契約不適合責任免責」の特約があるということは、売主が本来負うべきそうした契約不適合責任を免れるということです。
中古のビルやマンション等で、「契約不適合責任免責」を条件としている物件を見たことがある方も多いでしょう。このような、本来売主が負うべき責任を免責する特約が有効なのでしょうか。関係する法律に照らして見てみましょう。
民法による規定
民法では、このような売主に課せられる責任については、当事者間の特約により軽減し、または免除することができるとされています。つまり「契約不適合責任免責」の特約は、原則として有効です。
ただし、売主が知っていたのに告げなかった事実については免責されません。このような不誠実な売主の態度は法的保護には値しないからです。このため契約書の特約で「契約不適合責任」がうたわれていても、売主が承知している不具合については免責されることはありません。
宅地建物取引業法(宅建業法)による制限
売主が、宅地建物取引業者(宅建業者)である場合は、民法の規定と比べて買主が不利になる特約は無効となります。ただし、物件の引き渡しから2年以上は契約不適合の責任を追及できるという特約はできます。したがって、宅建業者が宅建業者でない個人の買主に対して不動産を売却する際、「契約不適合責任免責」の特約を付すことはできず、このような特約があっても無効となります。なお、この宅建業法による規制は一般消費者保護がその趣旨であるため、売主も買主も宅建業者である場合は適用されず、免責特約も有効です。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)による制限
売主が宅建業者ではないが、施工業者や販売会社から新築アパートを購入する場合には、上記の免責特約は有効なのでしょうか。
新築住宅の売買にあたっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の適用を受けることになります。この品確法では、売主は買主に対して、新築住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の不具合について、民法に規定する契約不適合責任を負う旨が定められています。そして、この規定より買主に対し不利な特約等は無効とされます。
したがって、新築アパート等を購入する場合、売主が宅建業者でなくとも、売主の施工業者や販売業者である場合は、上記の免責特約は無効となります。
免責特約が有効となる場合の買主としての注意点
売主が個人の場合や、宅建業者ではない業者が売主として中古物件の取引をする場合は、契約不適合責任免責の特約は有効となります。
このような免責特約がある物件は、近隣物件と比較して安価な価格で販売されているため、魅力的に見えることがあります。買主としては、まずは価格や利回りなどを見て物件を選択しがちですが、値段には相応の理由があります。
そこで、価格が比較的安価で魅力的な物件を見たら、まずは当該特約がないかどうかを確認します。免責特約があり、売主が宅建業者である場合は、個人の買主はそもそもターゲットとされていないこともあります。
売主が個人で、しかも免責特約があるということは、買主としては不具合があっても責任追及できないというリスクがあることを意味します。そのリスクを承知のうえで、なお購入を検討したい物件であれば、その特約の内容をきちんと確認するようにします。免責の内容も物件によりさまざまです。
また、物件調査も必要です。アパートを建てるために土地を購入するのであれば、建物が安全に建てられる土地なのか、配管や埋蔵物等を調べる必要があります。建物であればインスペクションという調査を建築士などの専門家に依頼することになります。
もちろん費用がかかるので、不動産価格が安価であってもその費用を上乗せしてなおリーズナブルといえるかを検討する必要があります。
今回解説したように、不動産取得に至るまで、煩雑な手続きや調査等を要するケースは少なくなく、適切に対応しなければ、契約当事者間に意思表示の合致があっても契約が思い通りに進まなくなってしまうこともあります。個々の物件の事情をきちんと把握し、最低限持つべき知識を持って、取引にあたることが大切です。 金銭を投じることで一旦目的を果たせる他の投資とは異なり、不動産投資は不動産取引という法律行為と、不動産経営という事業を継続的に行うことに他なりません。厳しい取引規制を敷かれた不動産を取引の対象とするということを肝に銘じて、取引当事者として主体的に、取引及び事業を進めていただければと思います。

住宅資材販売の会社で建具店、工務店、建設会社、ハウスメーカー、デベロッパー、設計事務所、ゼネコンを中心にルートセールスおよび新規顧客開拓に従事したのち、2013年に司法書士試験合格。
大手司法書士法人を経て、2018年に司法書士ゆかり事務所開業を開業。
司法書士(東京司法書士会所属)、行政書士(東京都行政書士会所属)、CFP®認定者(ファイナンシャル・プランナー)、宅地建物取引士。
【特集一覧はこちら:後悔しないための不動産投資取引に必要な法務・実務の基礎知識】
| manabu不動産投資に会員登録することで、下の3つの特典を受け取ることができます。 ① ウェビナー案内メールが届く ② オススメコラムのお知らせが届く ③ クリップしてまとめ読みができる |
- コラムの注意事項 -
- コラムに関する注意事項 - 本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。 当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。 外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。 本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。