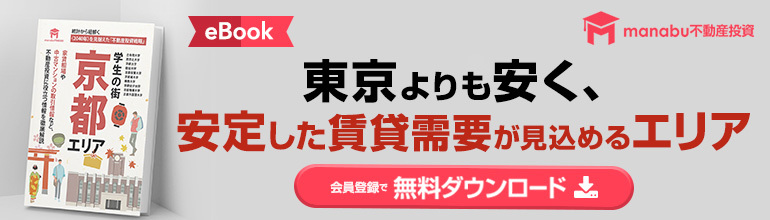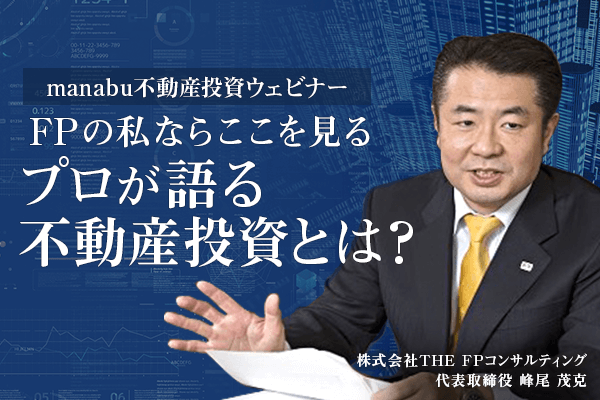不動産投資の利回りとは、物件購入金額に対して得られた家賃収入の割合のことである。物件選びの1つの指標ではあるが、利回りだけで物件の良し悪しを判断しないことが重要である。
本コラムでは、不動産における利回りの種類とその計算方法、利回りの目安、利回りだけで物件を判断しないほうがいい理由などについて詳しく解説していく。
- 不動産投資の利回りとは?
- 利回りの種類は主に6つ
- 表面利回り(グロス利回り):年間賃料収入を物件価格で割り戻して算出した収益割合のこと
- 実質利回り(ネット利回り):表面利回りから経費を差し引いた収益割合のこと
- 満室時想定利回り、現行利回りとは?
- 税引き前利回り、税引き後利回りとは
- ローン返済を加味するにはCCR・ROI
- 利回りの計算方法と具体例
- 不動産投資の期待利回りの目安
- 「ワンルーム」より「ファミリー向け」がやや高い
- 「首都圏」より「地方」のほうが高い
- エリア別に見ると注目の「札仙広福」の期待利回りが高い
- 将来の期待利回りの高いエリアを見極めるには減少率の幅をチェック
- 最低ラインの目安は投資目的によって異なる
- 不動産の種類別期待利回り
- 新築・中古区分マンションの利回り比較
- 高利回り物件を選ぶ際のリスクについて
- 利回り以外にも立地や築年数など総合的な判断を
- 利回りに関するQ&A
- Q.新築物件と中古物件で利回りに差があるのはなぜか?
- Q.物件の構造によって利回りに差はあるのか?
- Q.自己資本利回りとは何か?
- Q.不動産投資における利回りとは?
- Q.不動産投資の利回りは何パーセント?
不動産投資の利回りとは?
利回りとは、投下資金に対する利益の割合であり、不動産投資においては物件購入金額に対して家賃収入がどれくらいあったかを表す指標のことだ。
基本的には「年間家賃収入÷購入価格」で計算している場合が多いが、以下に紹介するように経費や税金、ローン返済を含むか否かでさまざまな計算方法がある。まずは、利回りの種類について確認しておこう。
利回りの種類は主に6つ
不動産投資における利回りの種類は主に以下の6つが挙げられる。
それぞれ計算方法が違うため、違いを理解して、物件を購入する際に活用しよう。
それぞれについて説明していこう。
表面利回り(グロス利回り):年間賃料収入を物件価格で割り戻して算出した収益割合のこと
表面利回りとは満室想定での賃料収入を利用するためグロス利回りとも呼ばれており、年間の賃料収入を不動産の購入金額で割り戻して算出した収益割合のことだ。経費を含めないため、計算方法が非常にシンプルで、一般的に投資用不動産を購入際の利回りは表面利回りが示されていることが多い。
経費を含めず計算する分、実際の収益割合より数値が高くなるので注意が必要だ。
実質利回り(ネット利回り):表面利回りから経費を差し引いた収益割合のこと
実質利回りとは、年間賃料収入から諸経費を差し引いた実質的な収益を、物件価格と物件購入時にかかった経費を足した数字で割って計算することで算出される。諸経費とは、固定資産税や管理委託費、修繕費用、修繕積立金、火災保険料などが挙げられる。また、物件購入時の経費としては、登録免許税や不動産取得税、印紙税、不動産仲介手数料などが挙げられる。
実質利回りを計算する際には、経費をどこまで考慮して算出するか判断する必要がある。
経費を含む利回りのため、表面利回りよりも現実的な利回りなので、事業計画などを立てるときは実質利回りを参考にすることが重要だ。
満室時想定利回り、現行利回りとは?
不動産投資の世界では、ここまで紹介してきた「表面利回り」と「実質利回り」がよく使われる。このほかにも不動産投資の利回りには「満室時想定利回り」や「現行利回り」もある。これらが使われるケースもあるので内容を覚えておきたい(特に想定利回りは頻出する)。
満室時想定利回りとは?
満室時想定利回りとは、対象物件が満室かつ想定した年間家賃収入が得られることを前提にした利回りのことだ。なお、物件購入時の諸経費や年間諸経費(管理委託料、共用部の光熱費、固定資産税・都市計画税など)を引く前の利回りとなる。
満室時想定利回りをチェックする際の注意点は、あくまでも見込みで計算した利回りなので、そのとおりにならないこともあることだ。例えば、稼働率100%の年間賃料収入を前提に想定利回りを計算していたが、実際には稼働率が50%しかなかったといった具合だ。
現行利回りとは?
現行利回りとは、現在の年間賃料収入をもとに計算した利回りのことだ。現在、2部屋が空室の場合は、その賃料をもとに年間賃料収入を計算する。より実際に近い数値と言えるだろう。
現行利回りをチェックする際の注意点は、賃料が低下する、あるいは稼働率が下がるなど前提条件が崩れるとギャップが生じることだ。例えば、物件購入時点の2部屋が空室という状況が続くとして年間家賃収入を504万円と想定していたが、物件購入後にもう1部屋空室になり年間賃料収入が420万円に下がったといった具合だ。もちろん、空室であった2部屋が稼働し、収入が上がることもある。
「満室時想定利回り」や「現行利回り」は参考でしかない
端的に言えば、満室時想定利回りや現行利回りを目安にして物件を購入するのは避けるべきだろう。なぜなら、これらはあくまでも「見込み」の家賃賃料や「過去」の稼働率に基づいたものだからだ。そのため、購入時よりも家賃や稼働率が悪化すると年間賃料収入が変動し、利回りも変わってしまう。
満室時想定利回りや現行利回りは、「もし、満室経営ができれば(または、その時点の稼働率に基づけば)これくらいの年間賃料収入が得られるのか」くらいの参考情報として扱うのが無難だろう。
税引き前利回り、税引き後利回りとは
不動産投資の収益から経費を引いた不動産所得に対してかかるのが、所得税や住民税だ。最終的に税金を差し引いた利回りが税引き後利回りとなる。
不動産広告に表示されている利回りは、多くが税引き前利回りである点に注意が必要だ。所得税と住民税は、以下の計算式で計算する。課税所得金額は、不動産所得を含むすべての所得を合算した金額である。
・所得税
課税所得金額×税率-税率控除額
・住民税
均等割(一般的に5,000円)+所得割(前年の所得の10%)
なお、住民税の均等割と所得割の基準は自治体によって異なる場合があるため、確認が必要だ。ほかにオフィスや店舗など事業用物件を貸している場合は、家賃に対して消費税が課税される。アパート・マンションなど居住用物件のみを貸している場合は非課税だ。
ローン返済を加味するにはCCR・ROI
融資を受けて物件を購入した場合は、ローン返済を加味した利回りを計算するとより詳細にシミュレーションできる。その際に使う指標がCCR(自己資本利益率)とROI(投資利益率)だ。
CCR(自己資本利益率)
CCRは、投資金額から融資金額を差し引いた自己資金に対するキャッシュフローの割合を表す指標だ。数字が高いほど投資した自己資金に対して効率よく稼いでいることになる。
「年間キャッシュフロー÷購入時自己資金×100」で算出可能だ。
ROI(投資利益率)
ROIは、自己資金と融資金額を合計した金額に対するキャッシュフローの割合を表す指標だ。計算式は「年間キャッシュフロー÷購入資金の総額×100」である。
なお、年間キャッシュフローは「年間家賃収入-(年間諸経費+ローン返済額)」で算出可能だ。
利回りの計算方法と具体例
表面利回り(グロス)の計算式と具体例
・表面利回りの計算式
表面利回りの計算式は以下になる。
「表面利回り(%)=年間賃料収入÷物件価格×100」
・表面利回りの具体例
例えば、4,000万円の物件で、年間賃料収入が160万円の場合の計算は以下になる。
160万円(年間賃料収入)÷4,000万円(物件価格)×100=4%

ただし、計算において経費を含まずに計算するため、正確性に欠けるので注意が必要だ。物件選びの際は指標の1つとして参考にしよう。
実質利回り(ネット)の計算式と具体例
・実質利回りの計算式
実質利回りの計算式は以下になる。
「実質利回り(%)=(年間家賃収入-年間諸経費)÷(物件価格+購入時の諸経費)×100」
・実質利回りの具体例
上記と同じ物件で実質利回りを計算してみよう。
【前提条件】
物件価格:4,000万円
年間の賃料収入:160万円
年間の経費:50万円
物件購入時の経費(※購入時の諸経費とは、登記費用、不動産取得税といった税金、不動産仲介手数料、ローン手数料などのこと):400万円
(160万円−50万円)÷(4,000万円+400万円)×100=2.5%

上記のように経費を含めた計算になるため、より現実的な収益率と言える。
実質利回りの年間諸経費一覧
不動産投資の実質利回りを求めるときに大事なことは、年間諸経費の金額を漏れなく正しく計上することである。必要な経費項目が抜け落ちてしまうと、実際の利回りとの誤差が出てしまうため要注意だ。例えば、木造アパート(1LDK/10戸程度を想定)の年間諸経費の主な項目、発生頻度、目安をまとめると以下のようになる。
<実質利回りの年間諸経費項目の例>
| 内容 | 発生頻度 | 年間諸経費の目安 |
|---|---|---|
| 管理会社に支払う管理委託料 | 毎月 | 戸あたり賃料の3~7% |
| 共用部の光熱費 | 毎月 | 一棟あたり5,000円~2万円程度 |
| 修繕積立金 | 毎年 | 一戸あたり9万円程度 (初年度~10年目:90万円が目安) |
| 入居時にかかる仲介手数料や広告料(AD) | その都度 | 戸あたりその都度発生 手数料/上限 0.5ヵ月分など 広告料/家賃の0~5ヵ月分 |
| 原状回復費 | その都度 | 内容による |
| 固定資産税、都市計画税 | 毎年 | 立地による |
| 火災保険料 | 毎年 | 一棟あたり7万円~ (あくまでも目安。補償内容による) |
| 共用部清掃費 | 毎月 | 頻度や業者による |
※修繕積立金は国土交通省「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」参照
※仲介手数料は借主と貸主双方の合計で1ヵ月分が上限
※火災保険料を5年分一括で支払った場合は、毎年かかる保険料を算出
「年間諸経費がいくらになるか」についてはケースバイケースだが、ここではアパート経営の諸経費の一例を挙げてみよう。
【前提条件】
木造アパート10戸(1LDK)
家賃9万円/戸あたり月
入居者退去の発生数/年間2回
| 項目 | 金額(年間) | 備考 |
|---|---|---|
| 管理委託料 | 54万円 | 家賃の5%で計算 9万円×5%×10戸×12ヵ月 |
| 共用部光熱費 | 12万円 | 月1万円で計算 |
| 修繕積立金 | 90万円 | 10年間の修繕積立金900万円で計算 |
| 仲介手数料 | 18万円 | 家賃1ヵ月分×2回で計算 |
| 広告料(AD) | 18万円 | 家賃1ヵ月分×2回で計算 |
| 原状回復費 | 20万円 | 1回10万円×2回で計算 |
| 固定資産税・都市計画税 | 30万円 | |
| 火災保険料 | 7万円 | |
| 共用部清掃費 | 14万4,000円 | 月1万2,000円で計算 |
| 総計 | 263万4,000円 |
このように、不動産投資にかかる年間諸経費を割り出してみるとかなりの金額になる。この諸経費を無視した表面利回りだけで物件購入を検討するのはリスクがあると言えるだろう。各項目の細かい金額がわからない場合は、概算でも構わないので実質利回りを算出して物件を検討することが重要だ。
以下のコラムではアパート経営に注目し、利回りの理想や最低ラインについて詳しく解説している。
【関連記事】アパート経営の利回りの理想と最低ラインは?安定化には経費率が大事
満室時想定利回り、現行利回りの計算式と具体例
満室時想定利回りの計算式
満室時想定利回りの計算式は、表面利回りと同じ「現行の年間賃料収入÷物件価格×100」だ。この年間賃料収入の部分が見込みになる。
満室時想定利回りの具体例
物件価格:9,000万円
部屋数:8部屋
家賃:7万円
稼働率100%:672万円(8部屋×7万円×12ヵ月)÷9,000万円×100%=7.46%
稼働率50%:336万円(4部屋×7万円×12ヵ月)÷9,000万円×100%=3.73%
現行利回りの計算式
現行利回りの計算式も表面利回りと同じだ。物件購入時の諸経費や年間諸経費を差し引かないで「年間賃料収入÷物件価格×100」で計算する。
現行利回りの具体例
物件価格:9,000万円
部屋数:8部屋
家賃:7万円
物件購入時点:2部屋が空室
物件購入後:3部屋が空室
物件購入時点:6部屋×7万円×12ヵ月=504万円÷9,000万円×100%=5.6%
物件購入後:5部屋×7万円×12ヵ月=420万円÷9,000万円×100%=4.60%
不動産投資の期待利回りの目安
購入物件を検討する際に、利回りの目安を把握しておくことは重要な判断材料となる。利回りの目安を表す指標の1つに「期待利回り」がある。「期待利回り」は、賃貸物件の取得に要した費用に対して期待される純収益の投下資本に対する割合のことを指す。
一般財団法人日本不動産研究所が行った「第49回不動産投資家調査」(2023年10月現在)によると、以下のような期待利回りの目安が分かる
「ワンルーム」より「ファミリー向け」がやや高い
全国主要都市のワンルーム賃貸住宅とファミリー向け賃貸住宅の期待利回りは下表のとおりである。ワンルームとファミリー向けで大きな差はないが、ややファミリー向けの期待利回りが高い傾向が見える。
| 地区 | ワンルーム | ファミリー向け |
|---|---|---|
| 札幌 | 5.0% | 5.0% |
| 仙台 | 5.0% | 5.1% |
| 東京城南地区 | 3.8% | 3.8% |
| 東京城東地区 | 4.0% | 4.0% |
| さいたま | 4.6% | 4.6% |
| 千葉 | 4.7% | 4.8% |
| 横浜 | 4.4% | 4.4% |
| 名古屋 | 4.5% | 4.6% |
| 京都 | 4.7% | 4.8% |
| 大阪 | 4.4% | 4.4% |
| 神戸 | 4.8% | 4.9% |
| 広島 | 5.2% | 5.2% |
| 福岡 | 4.6% | 4.6% |
「首都圏」より「地方」のほうが高い
首都圏と地方の平均期待利回りは下表のとおりである。ワンルーム、ファミリー向けどちらも地方の期待利回りのほうが首都圏より高い傾向がうかがえる。ただし首都圏は、一般的に物件価格が高いため利回りは低くなるが、その分賃貸需要が旺盛なため空室リスクも低い。どちらのメリットを重視するかで選ぶエリアを決める必要がある。
| ワンルーム | ファミリー向け | |
|---|---|---|
| 首都圏平均 | 4.26% | 4.36% |
| 地方平均 | 4.78% | 4.83% |
出典:一般財団法人日本不動産研究所「第49回不動産投資家調査(2023年10月現在)」※この先は外部サイトに遷移します。より株式会社ZUU作成
エリア別に見ると注目の「札仙広福」の期待利回りが高い
期待利回りが高いエリアと低いエリアのトップ3をまとめると以下のようになる。
<期待利回りが高いエリア>
| 順位 | ワンルーム | ファミリー向け | ||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 期待利回り | 地区 | 期待利回り | |
| 1位 | 広島 | 5.2% | 広島 | 5.2% |
| 2位 | 札幌・仙台 | 5.0% | 仙台 | 5.1% |
| 3(4)位 | 神戸 | 4.8% | 札幌 | 5.0% |
期待利回りの高いエリアについて、地域的な傾向は見えないが、地方都市として注目されている「札仙広福」がトップ3となった。再開発などで注目されているとはいえ、やはり物件価格の安さが要因と考えられる。
札仙広福については以下のコラムで詳しく解説している。
【関連記事】「札仙広福」で人気の間取りは?戸数の多い住宅の種類と延床面積で比較!
<期待利回りが低いエリア>
| 順位 | ワンルーム | ファミリー向け | ||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 期待利回り | 地区 | 期待利回り | |
| 1位 | 東京城南地区 | 3.8% | 東京城南地区・東京城東地区 | 4.0% |
| 2位 | 東京城東地区 | 4.0% | 横浜・大阪 | 4.4% |
| 3(5)位 | 横浜・大阪 | 4.4% | さいたま・福岡 | 4.6% |
逆に低いエリアは東京・大阪といった3大都市圏であり、これは地方都市に比べて物件価格が高いことから低利回りになっていると考えられる。
不動産価格の推移については以下のコラムで詳しく解説している。
【関連記事】不動産価格の推移がわかる「不動産価格指数」と「公示価格」を知ろう
将来の期待利回りの高いエリアを見極めるには減少率の幅をチェック
利回りを見る際には、過去の利回りの推移を基に今後どうなるか分析することが必要だ。一般財団法人日本不動産研究所の「不動産投資家調査」によると、期待利回りの推移は以下のとおりだ。
単位:%
| 年 | 東京 | 札幌 | 仙台 | さいたま | 千葉 | 横浜 | 名古屋 | 京都 | 大阪 | 神戸 | 広島 | 福岡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城南地区 | 城東地区 | ||||||||||||
| 2010 | 6.0 | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 7.3 |
| 2011 | 5.8 | 6.0 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.7 | 7.1 |
| 2012 | 5.8 | 6.0 | 7.7 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.7 | 7.1 |
| 2013 | 5.7 | 5.9 | 7.6 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
| 2014 | 5.6 | 5.8 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 7.0 |
| 2015 | 5.5 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 7.5 | 6.8 |
| 2016 | 5.4 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 6.7 |
| 2017 | 5.2 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
| 2018 | 5.1 | 5.4 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | 6.3 |
| 2019 | 5.0 | 5.2 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 6.1 |
| 2020 | 4.9 | 5.1 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 6.6 | 6.0 |
| 2021 | 4.7 | 5.0 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 5.8 |
| 2022 | 4.7 | 4.9 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 5.7 |
| 2023 | 4.6 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 5.6 |
出典:一般財団法人日本不動産研究所「不動産投資家調査」※この先は外部サイトに遷移します。より株式会社ZUU作成
2010年4月以降、すべてのエリアで右肩下がりに推移している。期待利回りは今後も下落を続ける可能性はあるが、なるべく減少幅が小さいエリアを見極めたいところだ。下記は減少率の少ない順にランキングしたものだ。
<2010年4月から2023年4月までの利回り減少率が少ないエリア>
| 順位 | エリア | 減少率(%) |
|---|---|---|
| 1位 | 広島 | 32.47 |
| 2位 | 千葉 | 32.86 |
| 3位 | 神戸 | 33.33 |
| 4位 | 京都 | 33.80 |
| 5位 | さいたま | 34.29 |
| 6位 | 横浜 | 34.33 |
| 7位 | 東京城東地区 | 35.48 |
| 8位 | 名古屋 | 35.71 |
| 9位 | 札幌・仙台 | 35.90 |
| 11位 | 東京城南地区 | 36.67 |
| 12位 | 福岡 | 36.99 |
| 13位 | 大阪 | 37.14 |
出典:一般財団法人日本不動産研究所「不動産投資家調査」※この先は外部サイトに遷移します。より株式会社ZUU作成
これを見ると広島、千葉、神戸の減少率が少ないことがわかる。今後もこの3エリアの利回り減少率が少ないとは限らないが、一つの判断材料になるだろう。最新の数値だけでなく これまでの推移も参考にしながら、将来性のある物件を見極めていきたい。
最低ラインの目安は投資目的によって異なる
利回りは高いほうがいいが、投資目的によってその最低利回りのラインが異なってくることを認識しよう。
不動産投資には、
- キャピタルゲイン(売却益)を得たい
- インカムゲイン(家賃収入)を得たい
- 相続税対策として所有したい
- インフレ対策として所有したい
など、さまざまな目的で不動産投資をしている方がいる。
例えば、投資目的がキャピタルゲイン(売却益)の場合は、利回りよりも不動産価格が上昇する可能性が高い立地を選択することが重要だ。
一方でインカムゲインの場合は、長期的に安定した収入を得ることが目的になるため、利回りが重要なポイントになってくる。
また、相続税対策やインフレ対策として不動産投資をする場合は、現金よりも不動産を持つことのメリットが大きいから、利回りはそこまで重要視するポイントではなくなる。
このように投資する目的によって最低利回りが異なるので、自分が不動産投資をする目的に合った物件を選ぶことが重要になる。
不動産の種類別期待利回り
不動産の種類によっても期待利回りは異なる。ここでは、賃貸住宅以外の施設の期待利回りを見てみる。
商業店舗の期待利回り
下表の東京都内は銀座地区(3.4%)、表参道地区(3.5%)、東京近郊は東京都心まで1時間程度の主要幹線道路沿いの店舗だ。期待利回りは、郊外型店舗のほうが高いことがはっきり見てとれる。
| 地区 | 都心型高級専門店 | 郊外型ショッピングセンター |
|---|---|---|
| 札幌 | 5.3% | 6.3% |
| 仙台 | 5.4% | 6.3% |
| 東京都内 | 3.4~3.5% | - |
| 東京近郊 | - | 5.2% |
| さいたま | 5.2% | 5.8% |
| 千葉 | 5.3% | 5.9% |
| 横浜 | 4.5% | 5.5% |
| 名古屋 | 4.7% | 5.8% |
| 京都 | 4.8% | 6.0% |
| 大阪 | 4.4% | 5.5% |
| 神戸 | 5.0% | 6.0% |
| 広島 | 5.4% | 6.3% |
| 福岡 | 4.7% | 5.9% |
物流施設、倉庫の期待利回り
立地条件は、幹線道路や高速I.C.へのアクセスが良好な地区としている。シングルテナント型は、2~3階(延床面積1万平方メートル程度)の物件を想定。マルチテナント型は、4テナントで3~4階(延床面積5万平方メートル程度)の物件を想定している。大きな差はないが、東京と大阪の利回りは低い傾向だ。
| 物流施設・倉庫の種類 | 立地条件 | 期待利回り | |
|---|---|---|---|
| シングルテナント型 | 湾岸部 | 東京(江東地区) | 3.8% |
| 名古屋(名古屋港地区) | 4.5% | ||
| 大阪(大阪港地区) | 4.3% | ||
| 福岡(博多港地区) | 4.5% | ||
| 内陸部 | 東京(多摩地区) | 4.1% | |
| 千葉(成田地区) | 4.6% | ||
| 名古屋(名古屋市北部) | 4.6% | ||
| 大阪(東大阪周辺) | 4.4% | ||
| 福岡(福岡IC周辺) | 4.6% | ||
| マルチテナント型 | 湾岸部 | 東京(江東地区) | 3.8% |
| 名古屋(名古屋港地区) | 4.5% | ||
| 大阪(大阪港地区) | 4.3% | ||
| 福岡(博多港地区) | 4.5% | ||
| 内陸部 | 東京(多摩地区) | 4.1% | |
| 千葉(成田地区) | 4.6% | ||
| 名古屋(名古屋市北部) | 4.6% | ||
| 大阪(東大阪周辺) | 4.3% | ||
| 福岡(福岡IC周辺) | 4.6% | ||
宿泊特化型ホテルの期待利回り
最寄り駅から徒歩5分以内、築5年未満で100室程度、稼働率80%以上のホテルを想定している。ホテルでは東京がほかの地区に比べて利回りが低いのが特徴的だ。
| ホテルの種類 | 立地条件 | 期待利回り |
|---|---|---|
| 宿泊特化型ホテル | 東京(JR線・地下鉄の主要駅周辺) | 4.4% |
| 札幌(JR札幌駅周辺) | 5.2% | |
| 仙台(JR仙台駅西口周辺) | 5.5% | |
| 名古屋(栄地区) | 5.1% | |
| 京都(JR京都駅烏丸口周辺) | 4.8% | |
| 大阪(JR新大阪駅周辺) | 4.8% | |
| 福岡(JR博多駅周辺) | 5.0% | |
| 那覇(那覇市国際通り周辺) | 5.2% |
新築・中古区分マンションの利回り比較
前述にも述べた通り、利回りをシミュレーションする方法は、諸経費を含まない「表面利回り」と年間家賃収入から諸経費を差し引いて計算する「実質利回り」の2つがある。
ここでは、新築区分マンションと中古区分マンションの利回りを比較してみよう。なお、年間諸経費は一般的な相場とされる家賃の20%相当とした。
新築区分の場合
【前提条件】
物件タイプ:3LDK
購入価格:6,000万円
年間想定家賃収入:264万円(月22万円×12ヵ月)
購入時諸費用:600万円
年間諸経費:52万8,000円(家賃の20%相当)
【計算例】
・表面利回り
(22万円×12ヵ月÷6,000万円)×100=4.40%
・実質利回り
{(22万円×12ヵ月-52万8,000円)÷(6,000万円+600万円)}×100=3.20%
中古区分の場合
【前提条件】
物件タイプ:3LDK
購入価格:4,200万円
年間想定家賃収入:216万円(月18万円×12ヵ月)
購入時諸費用:400万円
年間諸経費:43万2,000円(家賃の20%相当)
【計算例】
・表面利回り
(18万円×12ヵ月÷4,200万円)×100=約5.14%(小数点第3位四捨五入)
・実質利回り
{(18万円×12ヵ月-43万2,000円)÷(4,200万円+400万円)}×100=約3.76%(小数点第3位四捨五入)

シミュレーションの結果、中古マンションのほうが高い利回りになった。一般的に新築物件と中古物件を条件が近い状態で比較した場合、中古物件のほうが高利回りになりやすい。理由は新築物件の物件価格のほうが比較的高いからだ。しかし賃貸需要は、新築マンションのほうが高いため、空室リスクを考慮すると新築のほうが有利になる場合がある。そのため単に利回りだけを見て中古のほうがお買い得と考えるのは早計だ。
高利回り物件を選ぶ際のリスクについて
利回りは収益率の1つの指標になるため、利回りが高い物件を選んでしまう方も多い。しかし、表面利回りだけで物件を選ぶことは非常に危険なのだ。
その理由として、主に3つ挙げられる。
・表面利回りが高くても実質利回りが低くなることがあるから
・相場の利回りより高い場合はネガティブな要因が潜んでいる可能性があるから
・投資目的によって最低利回りが異なるから
表面利回りが高くても実質利回りが低くなることがある
前述したように表面利回りは経費を含んでいないため、実質利回りより高く見せることができる。販売図面やポータルサイトなどの物件情報に記載されているのは、ほとんどが表面利回りだ。そのため、表面利回りが高いという理由で選んでしまうと、実質利回りが表面利回りよりも低くなるので注意が必要だ。
再三にわたって解説しているが、改めて1つの例を挙げてみよう。
【前提条件】
物件価格:2億円
部屋数:10室
賃料収入:9万円/月
年間の経費:250万円
物件購入時の経費:2,000万円
・表面利回り
9万円×10(室)×12ヵ月=1,080万円(年間賃料収入)
1,080万円(年間賃料収入)÷2億円(物件価格)×100=5.4%
・実質利回り
9万円×10(室)×12ヵ月=1,080万円(年間賃料収入)
(1,080万円-250万円)÷(2億円+2,000万円)×100=約3.8%(小数点第2位四捨五入)
このように表面利回りは5.4%だが、実質利回りの約3.8%とおよそ1.6%の差がある。
したがって、表面利回りだけで物件を判断すると、思っていたよりも利益が出ないということになりかねない。こういった理由から、表面利回りだけで判断するのは危険と言える。
相場の利回りより高い場合はネガティブな要因が潜んでいる可能性がある
販売されている物件の中には、利回りが相場の利回りより高くなっている物件もある。利回りが高いから購入したい気持ちは分かるが、なぜ利回りが高いのかの理由を必ず確認することが必要だ。
一般的には物件の販売価格は相場を参考にしながら決めるケースがほとんどだが、売主に事情がある場合にはそれを加味して売却価格を設定することもある。
・売主が早く現金化したい、早く売りたいケース
この場合、売却価格を相場より低く設定することがある。売却価格は安くなったけど家賃は変わらないので、このような理由で利回りが相場の利回りより高くなる物件は購入を検討してもいい物件と言える。
・長期間の入居で当初の家賃が設定されているケース
この場合は注意しなければならない。理由として考えられるのは、入居者の入居期間が長く、家賃は当時の家賃相場で設定していたため、今の相場より高く得られたから利回りが高くなっているケースである。
そうすると、その入居者が退去したタイミングで経費がかかり、場合によっては相場に合わせて家賃を下げなければならず、結果として利回りが低くなる可能性がある。
また、賃貸需要があまり良くない地域で、満室想定の利回りを見て物件を購入してしまうと、想定していたよりも稼働率が上がらずに収益性がなかったということや、物理的、権利的、心理的な瑕疵が隠されているケースもある。
つまり、相場の利回りより高い場合は、掘り出し物件であるケースもあれば、落とし穴となるケースもあるので、まずはその理由を確認してみることが重要と言える。
利回り以外にも立地や築年数など総合的な判断を
上記のように、不動産投資は投資する目的によって最低利回りが異なる。つまり、自分の投資目的を達成できる物件を選ぶことが重要で、利回りはあくまでも1つの指標であることを認識しておくことが重要である。
不動産投資においては物件選びが非常に重要と言える。安定した家賃収入を得るには賃貸ニーズが高い物件を選ぶ必要がある。そのため、利回りのほかにも重視しないといけない次のような条件がある。
立地:駅へのアクセス・周辺環境など
不動産投資が成功するかどうかのカギを握るのが立地条件だ。例えば次のような条件が挙げられる。
- 最寄り駅から徒歩圏内であること
- 近くにスーパーなど商業施設があること
- ファミリー層向けなら学校、公園、病院が近いこと など
購入を検討している物件が想定する入居者に合わせた周辺環境かどうか調査し、空室リスクを低くすることが重要だ。
築年数:築古は修繕費がかかりやすい
建物は、築年数の経過とともに劣化するものだ。たとえ表面利回りが高い物件でも修繕費用が多くかかれば実質利回りは低下する。購入したい物件の築年数を確認し、リフォーム実績や修繕履歴も不動産仲介会社に聞いておくほうが無難だ。
重大な欠陥:事故物件などは空室リスクが高い
物件に告知義務に関わるほどの重大な欠陥がある場合は、入居者獲得に大きな影響を及ぼす。特に自殺があった事故物件や、地震や災害で生じた亀裂や傷みがある物件は入居者にとって大きなマイナスになるため、空室が発生しやすい。十分に確認する必要がある。
耐震基準:満たしていない物件は要注意
地震が頻発している現代においては、耐震基準がますます厳しくなっている。新築物件は、基準を満たさないと建築できないため問題ないだろう。しかし1981年6月以前の新耐震基準制定前の物件では、基準を満たしていない物件が残っている可能性がある。最悪建て替えが必要な場合もあるため、築古物件を購入する場合は要注意だ。
利回りは1つの指標として、ほかの条件と合わせて総合評価し、物件を選ぶことが重要だ。
利回りに関するQ&A
最後に、不動産投資の利回りをより深くご理解いただくために、初心者が疑問に感じることの多い「利回りに関するQ&A」をご紹介したい。
Q.新築物件と中古物件で利回りに差があるのはなぜか?
新築物件と中古物件を比較した場合、中古物件のほうが高利回りになりやすい(条件が近い物件の場合)。理由は新築物件の物件価格のほうが割高になるからだが、これは表面利回りの計算式(年間賃料収入÷物件価格×100)にあてはめて考えると分かりやすい。
例えば、下記のような同じ年間賃料収入の「新築物件」と「中古物件(築5年)」の収益物件があったとしたら、中古物件のほうが約1%高利回りになる。
| 比較項目 | 新築物件 | 中古物件(築5年) |
|---|---|---|
| 物件価格 | 1億2,000万円 | 1億円 |
| 年間賃料収入 | 650万円 | |
| 表面利回り | 5.41% | 6.5% |
ここでは話を分かりやすくするため、新築物件と中古物件の年間賃料収入を同額にしている。しかし実際には新築物件のほうが家賃を高めに設定しやすい点にも留意したい。また、中古物件は高利回りだが、建物が老朽化していたり、住宅附属設備が陳腐化していたりする点が考慮されていることも意識したい。
なお例外として、一等地のヴィンテージマンションなどでは、築年数が経っていても物件価格や賃料の変動が少ない(あるいは上がっている)ため、中古物件なのに低利回りの物件も存在する。
Q.物件の構造によって利回りに差はあるのか?
利回りは、物件価格が安いほど高利回りになりやすい。この物件価格に大きな影響を与えるのが建物構造だ。主な建物構造を建築費が高い順に並べると以下のようになる。
<建築費高=低利回り>
鉄筋鉄骨コンクリート
鉄筋コンクリート
鉄骨造
木造
〈建築費低=高利回り〉
利回りを建物という観点で捉えた場合、上記のような建築費(建物原価)に加えて、建物の経済的価値や残存する法定耐用年数などを考慮しながら最終的な利回りが決まる。
ちなみに、建物構造によって建築費の差がどれくらいあるかというと、国税庁がまとめた資料を参考にすると、(工事費ベースで)木造よりも鉄筋コンクリート造が1平方メートルあたり8万8,000円割高になる。
| 構造 | 全国平均 平方メートルあたり単価 (単位:円) |
|---|---|
| 木造 | 17万7,000円 |
| 鉄骨造 | 27万2,000円 |
| 鉄筋 コンクリート造 |
27万8,000円 |
| 鉄骨鉄筋 コンクリート造 |
26万5,000円 |
注意したいのは、建築費が高い建物になるほど家賃設定を高くしやすい点だ。例えば、木造のアパートと鉄筋コンクリート造のマンションを比較すると、マンションのほうが賃料収入を高くしやすい(条件が近い物件の場合)。
これを考慮すると、違う構造の収益物件を比較検討するのであれば、「木造は高利回り」「RC造は低利回り」と思い込まず、実際に利回りを算出して比べるのが無難だろう。
Q.自己資本利回りとは何か?
一般的に、不動産投資は融資を受けて物件を購入することが多い。例えば、9,000万円の物件を自己資金1,000万円+借入金8,000万円で購入するといった具合だ。そのときに、自己資金(1,000万円)に対する収益率を表したものが「自己資本利回り」である。
具体例を挙げてみよう。
物件価格:9,000万円
自己資金:1,000万円
借入金:8,000万円
部屋数:8部屋
家賃:7万円
表面利回り:672万円(8部屋×7万円×12ヵ月)÷物件価格9,000万円×100=7.46%
自己資本利回り:672万円(8部屋×7万円×12ヵ月)÷自己資金1,000万円×100=67.2%
仮に、自己資金を2,000万円とした場合、自己資金利回りは33.6%(672万円÷2,000万円×100)となる。このように、自己資金を多く入れると自己資金利回りは下がり、逆に少なくすると自己資金利回りは上がることになる。
なお、少額の自己資金で不動産投資をする場合、デメリットも発生するので注意が必要だ。例えば、融資額が増えることで毎月のローン返済額が多くなったり、借入時よりも金利が上昇すると返済総額が多くなったりすることがある。
Q.不動産投資における利回りとは?
不動産投資における利回りとは、物件購入金額に対して家賃収入がどれくらいあったかを表す指標のことだ。基本的には「年間家賃収入÷購入価格」で計算するが、経費や税金、ローン返済を含むか否かで以下のようにさまざまな計算方法がある。
<利回りの主な種類>
| 利回りの種類 | 概要 |
|---|---|
| 表面利回り | 年間の賃料収入を不動産の購入金額で割ったもの |
| 実質利回り | 年間の賃料収入から管理費・修繕積立金・固定資産税などの経費を差し引いた実質的な収益を、物件価格と物件購入時にかかった経費を足した数字で割って計算したもの |
| 満室想定利回り | 対象物件が満室かつ想定した年間家賃収入が得られることを前提にした利回り |
| 現行利回り | 現在の年間賃料収入をもとに計算した利回り |
| 税引き前利回り、税引き後利回り | 不動産投資の収益から経費を引いた不動産所得に対し、最終的に税金を差し引く前の利回りが税引き前利回り、差し引いた後が税引き後利回り |
そのほかにローン返済を加味してCCR(自己資本利益率)とROI(投資利益率)を使って利回りを計算する方法もある。
Q.不動産投資の期待利回りは何パーセント?
不動産投資の利回りは、一般財団法人日本不動産研究所が公表している「第48回不動産投資家調査」によると、全国主要都市の期待利回りは以下のとおりだ。
- ワンルーム賃貸住宅:3.8~5.2%
- ファミリー向け賃貸住宅:4.0~5.2%
- 都心型商業店舗:3.4~5.4%
- 郊外型商業店舗:5.2~6.3%
- 物流施設:3.8~4.6%
- 宿泊特化型ホテル:4.4~5.5%
「FPの私ならここを見る」 プロが語る不動産投資とは?
なぜ、今不動産投資なのか?
人生100年時代の資産形成の考え方や、不動産投資の「勝ち組」と「負け組」の紙一重の違いをFP歴20年以上、個別相談実績5,000件以上の経験豊富なFPの視点からわかりやすく解説します。
クリックして詳細を確認する

宮路 幸人
会計事務所での長い勤務経験で培った豊富な実務知識により、会計処理・税務処理および経営や税務に関する相談など、さまざまな問題に対応。宅地建物取引士、マンション管理士等の資格を保有し、不動産と相続関連に強みを発揮する。特に相続関連では、税務面だけでなく、家族の幸せを重視したトータルでの提案を行っており、軽いフットワークでお客さまのニーズに応えることをモットーとする。離島支援活動にも積極的。
- コラムに関する注意事項 -
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。
当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。
外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。