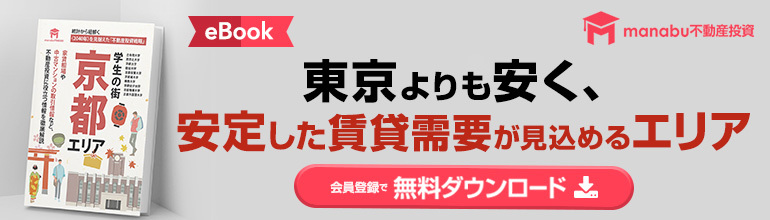賃貸物件で不動産経営をしている場合、「家賃収入に消費税はかかるのか」、「家賃収入に消費税が課税されない条件を知りたい」など、疑問に思っている人は多い。なぜなら、課税の有無で収支が大きく変わるためだ。
では、実際は家賃収入に対して課税されるのだろうか?
結論から言うと、居住用に貸し出しを行って家賃収入を得ている場合は消費税が非課税になる。だが、一方で事業用に貸し出している場合には課税されてしまう。
とはいえ、事業用に貸し出しているケースでも、家賃収入が「1,000万円」を超えない場合には消費税が課税されない。このように条件によっては課税になるケースもあれば、非課税になるケースもあるため、賃料収入に消費税が課せられる条件についてよく理解をしておくことが非常に重要だ。
この記事では、家賃収入に消費税が課せられる場合と、課税されない場合の条件など詳しく解説していく。 不動産経営を行っている方は、ぜひこの記事を最後まで読んで参考にしてほしい。
居住用物件の消費税は原則かからない
不動産経営において、居住用物件の家賃収入、礼金、管理費・共益費などの消費税は原則かからない。しかし、非課税になるには条件がある。
3つの条件を満たせば家賃収入の消費税はかからない
賃貸借契約書において不動産が住居として使用される場合は消費税がかからない。一方、事業用として契約した場合は消費税がかかるため注意が必要だ。
ちなみに、家賃収入で消費税を非課税とするための条件は以下の3つが挙げられる。
- 賃貸期間が1ヵ月以上であること
- 契約書に居住用と記載されていること
- 賃貸借契約書がないなど賃貸の用途が明らかでなくても居住の実態があること
つまり、契約書に居住用と記載されていた場合でも、賃貸期間が1ヵ月間未満の場合は消費税が課せられる。また、ホテルやウィークリーマンションは1ヵ月以上の場合でも消費税の課税対象になる。
一方で、会社が社宅として賃貸借契約を行っている場合は、賃貸借契約に「従業員が居住する」という記載があれば居住用物件になるため、消費税は課税されない。また、2020年度の税制改正により、2020年4月1日から、賃貸借契約書がなく賃貸の用途が明らかにされていなくても、実態からみて居住用だと分かるときも非課税だ。
礼金・更新料も消費税はかからない
家賃収入と同様、賃貸オーナーが受け取る居住用の礼金・更新料も、原則消費税はかからない。
敷金は、退去時に入居者(借主)が負担すべき修繕費を差し引くような一般的な敷金であれば、預かり金扱いになるため消費税は不課税になる。
一方の礼金は、入居者に返却する性格のものではないが、居住用物件のものなら消費税は非課税になる。ただし同じ礼金でも、事業用物件なら消費税の課税対象になる点に注意が必要だ。ちなみに事業用物件の場合、借主が法人でも個人でも、礼金は消費税の課税対象になる。

管理費や共益費も消費税がかからない
さらに、居住用マンションの場合に受け取る管理費や共益費は、居住するために必要な費用という点で家賃収入と同様に消費税がかからない。
家賃や共益費に水道光熱費が含まれている場合も消費税はかからない。
しかし、家賃とは別に一定額の水道光熱費を請求している場合や、使用実態に応じて料金を請求している場合は、消費税が課せられるため注意が必要だ。
このように投資用不動産を経営するうえで家賃収入や管理費、共益費の消費税が非課税になる場合についてはさまざまな条件があるため、よく理解しておく必要がある。
数多くの資産運用相談を受けてきた同氏が、資産運用のための情報収集方法、相談者の投資体験談など、さまざまなテーマを取り上げ、資産運用に対する適切な向き合い方や成功するための思考法がよくわかる内容です。
クリックして詳細を確認する
事業用賃貸の場合は消費税がかかる
前述したように賃貸用不動産を事業用として貸し出した場合は消費税がかかる。
住居兼事務所の場合はどうなるのだろうか?住居部分と事務所部分が分かれており、独立して使用できる場合は、事務所として使用されている部分が消費税の課税対象になる。一方で住居として主に使用されており、店舗、事務所も兼ねている場合は基本的に住居扱いになるため、消費税はかからない。
では、どういったものが住居として主に使用されていると判断されるのだろうか?それは、住宅の賃貸借契約において賃貸用途が「居住用」と記載されている場合は居住用と判断される。また、前述のとおり、2020年4月からは賃貸借契約書がないなど賃貸の用途が明らかにならない場合でも、居住の実態が明らかであれば居住用として判断される。
このように消費税の課税の有無については、賃貸借契約書に記載されている内容が重要になる。万が一、賃貸借契約書がない場合は居住の実態があるかどうかで判断される。
ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合には免税事業者とみなし、事業用として貸し出していても消費税の納税を免除してもらうことができる制度もある。
この場合の基準期間とは、個人事業者の場合は前々年の課税売上高のことを指し、法人の場合は前々事業年度の課税売上高のことを指す。
要するに、個人事業者や法人の場合でも1期目と2期目の消費税は免除されることになる。
しかし、以下の場合には消費税が課せられるため注意が必要だ。
- 前年の1月から6月までの課税売上高が1,000万円超(かつ給与支払額が1,000万円超)なら2期目でも消費税が免除されない
- 法人の場合は資本金が1,000万円以上の場合は消費税が免除されない
このように、事業用で賃貸借契約をしている場合でも、状況によって課税の有無が変わるため、仕組みをよく理解しておこう。なお、もともと消費税の非課税業者でも、状況が変わって 課税業者になったときには、所轄税務署への速やかな届け出が必要だ。届け出なくてはならない場合、以下のような例がある。
- 課税売上高が1,000万円を超えることとなったとき
- 資本金などが1,000万円以上の法人を設立するとき
- 消費税の免税事業者が課税業者を選択するとき など
店舗併設型のマンションの消費税はどうなる?
居住用と事業用が一体化した店舗併設型のマンションの場合、どのような扱いになるだろうか。これも「居住用物件=課税されない」「事業用物件=課税される」という基本は変わらない。例えば、以下のような店舗併設型のマンションがあったとしよう。
- 1階〜2階:店舗スペース
- 3階以上:住居スペース
この場合、1階〜2階の店舗部分で得られる家賃収入は消費税がかかり、3階以上の住居で得られる家賃収入は消費税がかからない。考え方自体は難しくないものの、実際の不動産経営では、同じ物件で「消費税あり、なし」が混在していると入退去時にケアレスミスが起きやすいため注意したい。
駐車場は貸し方によって消費税の課税対象にならない場合がある
駐車場を貸し出ししていると、基本的に賃料収入は消費税の課税対象となる。ところが、課税対象にならない場合もある。
それは地面の整備やフェンス、区画の設置を行っていない場合だ。例えば、極稀だが青空駐車場(屋根もなく地面が整備されていない駐車場)などのような、単なる土地という資本の貸付である場合は消費税がかからない場合もある。ただし、施設の利用に伴って土地が使用される場合と判断されるケースは課税対象になる。なかなか判断が難しいので、詳しくは専門家に相談するのが無難だろう。
では、住宅に併設する形の駐車場はどういった扱いになるのだろうか?基本的には課税対象であるが、以下の要件を満たした場合には非課税対象になるので覚えておきたい。
- 物件ごとに1台以上の駐車できる場所があること
- 入居者が自動車を保有していなくても駐車場所があること
- 駐車場の賃料を家賃に含めていること
ただし、駐車スペースが住宅から離れた場所に確保している場合は、消費税がかからない可能性があるため注意が必要だ。
ちなみに、マンションの場合は駐車場の賃料に消費税が課せられる可能性が高い。マンションは居住部分と駐車場部分で料金が分かれていることが多く、希望する居住者にのみ駐車場を貸し出しているケースが多いためだ。
とはいえ、住居部分の家賃収入は消費税がかからないため、基準期間内に駐車場収入だけで1,000万円を超えることはめったにないので、消費税の申告義務が免除されることが多い。
その他、消費税がかかる場合
入居者の希望により付帯された設備を貸し出している場合、その使用料は消費税の課税対象になる。
家具や家電、倉庫を入居者の希望によりレンタルしている場合は、その使用料が課税対象になる。ただし、入居者の選択にかかわらず、あらかじめ家具や家電、倉庫が設置されている場合は、消費税がかからない。
なお、倉庫の使用料金を家賃収入に含めずに別項目で請求している場合は、あらかじめ設置されている場合でも使用料に対して消費税がかかるため、注意が必要だ。
このように住居に付帯している設備であっても使用料が賃料に含まれている場合には消費税が課せられず、賃料とは別に請求する場合には消費税が課せられる。そのため、消費税がかからないようにするには、賃貸借契約書に記載する内容を慎重に吟味することが必要だ。
不動産経営で納める消費税の計算方法
消費税の納税額を計算するのは複雑なので、税理士に委託するのが無難だ。しかし賃貸オーナーとして、その基本や仕組みを知っておくことも大切である。
消費税の納税額計算の基本的な考え方
消費税の納付税額は、課税売上にかかった消費税から、課税仕入れなどにかかった消費税(=仕入控除税額)を控除して計算する。この計算で算出された金額がプラスなら消費税を納付、逆に、算出された金額がマイナスなら還付(お金が戻る)になる。ただし、課税事業者を選択する手続きを行っていない免税事業者については、還付の対象にならない。
消費税の納税額を計算する方式
消費税の納税額を計算する方式には、大きく「原則課税」と「簡易課税」がある。「原則課税」は、個別の取引などをもとに納税額を割り出す方式だ。また、「簡易課税」は、課税売上高から一定割合(みなし仕入れ率)を引いておおまかに納税額を割り出す方式である。
後者の簡易課税は、売上高5,000万円以下の中小企業を対象にしたものだ。売上高から差し引く「みなし仕入れ率」は業種ごとに6つに分かれ、40〜90%の設定がある。不動産賃貸業はこのうち、みなし率40%となっている。
「原則課税」と「簡易課税」どちらの方式が選べるかは、売上高などの条件によって違う。加えて、方式の選択によって、消費税の納税額が大きく変わる可能性もある。
いずれにしても、簡易課税を選ぶと2年以上継続しなければならないルールのため、どちらの方式を選択するのがベストかについては、税理士に相談しながら慎重に選ぶべきだろう。なお、簡易課税制度を選択するときは、その制度の適用を受けようとする「課税期間の初日の前日まで」に、管轄税務署に対して規定の届け出をしなければならない。
シンプルな操作で未来のキャッシュフローを簡単にシミュレーションできます。
キャッシュフローシミュレーターの3つのメリット
・2億超の不動産データに基づき、「賃料」や「空室率」をAIが算出
・最長50年間のキャッシュフローをわかりやすく確認
・地図上で物件の情報や最寄り駅の情報をまとめて確認
クリックして詳細を確認する
家賃収入不動産経営の消費税は、いつどのように支払う?
前述したように、事業用物件の場合の売上(家賃収入など)でも1期目と2期目は原則、消費税が免除される。
※ただし、前年の1月から6月までの課税売上高が1,000万円超(かつ給与支払額が1,000万円超)なら2期目は課税、また、資本金1,000万円以上の法人は1期目から課税
消費税の課税業者の賃貸オーナーが気になるのは、では3期目の消費税を「いつどのように支払えばよいのか」ということだろう。まず「消費税をいつ支払うのか」については、個人事業主と法人では期限の設定が違う。
| 形態 | 納付期限 |
|---|---|
| 個人事業主 | 対象年度の翌年の3月末まで ※口座振替の場合は4月下旬 |
| 法人 | 課税期間終了日の翌日から2月以内 |
次に「消費税をどのように支払えばよいか」については、所轄税務署に対し、地方消費税と消費税を併せて申告・納付するのが決まりとなっている。ちなみに、標準税率10%の場合、消費税率7.8%、地方消費税率2.2%の内訳になっている。
インボイス制度による不動産経営への影響とは?
不動産経営と消費税というテーマでは、2023年10月から始まる「インボイス制度」が見逃せない。特に 「事業用物件を経営+免税事業者」の賃貸オーナーは、インボイス制度の仕組みを理解して万全の対応する必要がある。まずはインボイス制度の概要を見てみよう。
インボイス制度と登録番号とは?
「インボイス(適格請求書)」とは、売手が買手に対して、利用される税率や消費税額を明確に伝える請求書(またはそのデータ)のことである。具体的には、請求書に以下の情報が明記されたものである。
- 登録番号
- 適用税率
- 消費税額など
上記のうちの登録番号は、所轄税務署に「適格請求書発行事業者」として登録することで発行されるものだ。インボイス制度においては、この部分が極めて重要だが「登録番号があることで、消費税の課税事業者の証明」になる。つまり、登録番号のない売手が発行した請求書はインボイスとして認められないということだ。なお、インボイス制度には、売手・買手それぞれに下記のような義務がある。ここも抑えたいポイントだ。
| 立場 | 義務 |
|---|---|
| 売手または サービス提供者 | ・買手から求められた場合に交付 ・交付したインボイスの写しを保管 |
| 買手または サービス受給者 | ・交付されたインボイスを保存 |
そして、買手は交付されたインボイスを保存することで、消費税の仕入税額控除が可能になる。
インボイス制度は不動産経営にどう関連する?
次に、このインボイス制度が、不動産経営の現場でどのように使われるかイメージしてみよう。一例では、入居企業(借主)が賃貸オーナー(貸主)に対して適格請求書の発行を依頼してくることが考えられる。
インボイス制度前であれば、賃貸オーナーが消費税の免税事業者でも、入居企業が支払った家賃の中に消費税が含まれるとみなされ、仕入税額控除が行えた。しかし、インボイス制度後は、賃貸オーナーが 「適格請求書発行事業者の登録をしているか否か」で状況が大きく変わる。
賃貸オーナーが適格請求書発行事業者の登録をしていれば、適格請求書が発行でき、これを受け取った入居企業は消費税の仕入税額控除が行える。これに対して、賃貸オーナーが登録をしていなければ、適格請求書が発行できない。つまり、入居企業が仕入税額控除を行えないことになる。これにより、賃貸オーナーへの以下のような要請が想定される。
- 適格請求書発行事業者の登録をしてほしい
- 家賃の値下げ(仕入税額控除分など)をしてほしい
このような要求に応えられなければ入居企業が退去し、空室率が高まる恐れもある。これを意識すると現在、消費税の免税事業者の賃貸オーナーは今後、適格請求書発行事業者の登録(=消費税の課税業者になる)を検討するのが無難かもしれない。
なお、適格請求書発行事業者の登録はすでに始まっている。詳しい内容を知りたい人は、国税庁の「インボイス制度 ※この先は外部サイトに遷移します。」公表サイトが参考になる。
シンプルな操作で未来のキャッシュフローを簡単にシミュレーションできます。
キャッシュフローシミュレーターの3つのメリット
・2億超の不動産データに基づき、「賃料」や「空室率」をAIが算出
・最長50年間のキャッシュフローをわかりやすく確認
・地図上で物件の情報や最寄り駅の情報をまとめて確認
クリックして詳細を確認する

宮路 幸人
会計事務所での長い勤務経験で培った豊富な実務知識により、会計処理・税務処理および経営や税務に関する相談など、さまざまな問題に対応。宅地建物取引士、マンション管理士等の資格を保有し、不動産と相続関連に強みを発揮する。特に相続関連では、税務面だけでなく、家族の幸せを重視したトータルでの提案を行っており、軽いフットワークでお客さまのニーズに応えることをモットーとする。離島支援活動にも積極的。
| manabu不動産投資に会員登録することで、下の3つの特典を受け取ることができます。 ① ウェビナー案内メールが届く ② オススメコラムのお知らせが届く ③ クリップしてまとめ読みができる |
- コラムに関する注意事項 -
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。
当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。
外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。