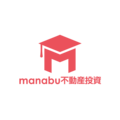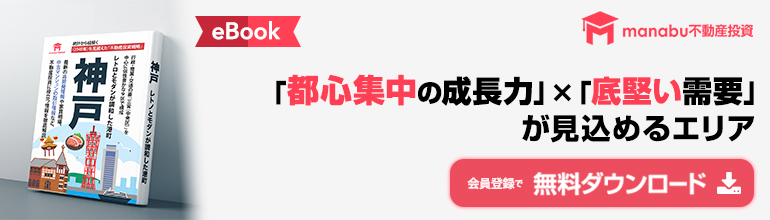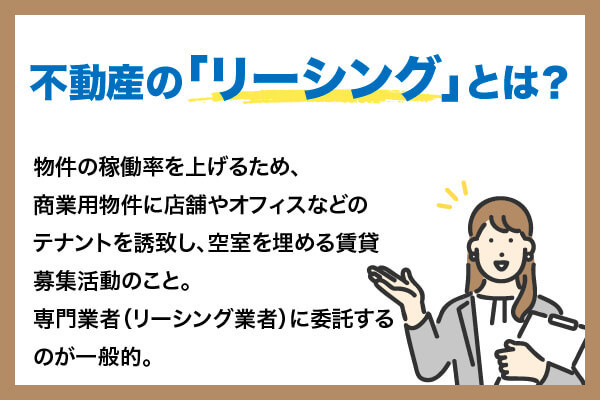
リーシングとは、商業用不動産におけるテナント誘致や賃貸借契約の仲介・調整を行う業務のことを指します。リーシングは不動産運用において非常に重要な業務であり、専門的な知識とネットワークが求められることから、専門業者に委託することが一般的です。
本コラムでは、リーシングの業務内容や、プロパティマネジメントとの違い、業者を活用するメリット・デメリットについて詳しく解説します。
不動産のリーシングとは

まずは、リーシングの定義やプロパティマネジメント(PM)・不動産仲介との違いについて解説します。リーシングは不動産投資の収益性を高めるうえで非常に重要な業務となるため、しっかりと基本的な知識を抑えるようにしましょう。
商業用物件に入居者(テナント)を誘致する業務のこと
リーシングとは、不動産仲介業務の一種であり、オフィスビルやテナントビルなど商業用不動産にテナントを誘致し、空室を埋めるための賃貸支援を行う業務です。物件の稼働率を上昇させることを目的としています。具体的には、周辺のマーケット調査を行い、適切な家賃を設定し、テナントの募集やテナントの誘致、オーナーと入居者の賃貸借契約の手助けなど、対象となるテナントの業種や規模に合わせて募集活動を展開します。
その後、問い合わせ対応や内見の調整、条件交渉などを通じて、最終的に賃貸借契約の締結に至るまでをサポートします。これらは単に空室を埋めるだけでなく、物件全体の魅力や収益力を高め、安定的な運用につなげるために不可欠なプロセスです。そのため、専門業者であるリーシング業者に委託することが一般的です。
不動産投資において、物件の稼働率は収益に直結する重要な指標であり、リーシングの巧拙が投資の成功を左右すると言っても過言ではありません。
プロパティマネジメントとの違い
プロパティマネジメント(以下、PM)は、物件の管理業務全般を指します。PMには、「リーシング業務」「レポート業務」「メンテナンス業務」「コンストラクションマネジメント業務」「アカウント業務」などの業務があり、その中で「リーシング業務」には、テナントの誘致や契約管理、空室対策などが含まれます。
PMは不動産のコストやテナントの管理、設備のメンテナンスなど物件全体の資産価値を維持したり向上させたりすることを目的としているのに対し、リーシングは特に空室を減らし、収益を高めるためのテナント募集活動に特化しているという点で異なります。
不動産運用を成功させるためには、この両者の連携が欠かせません。PMの業務内容や重要性、業者の選び方はこちらの記事で詳しく解説しています。
【関連記事】不動産のプロパティマネジメントとは?対応内容や種類・重要性を解説
賃貸住宅の仲介との違い
賃貸住宅の仲介は、主に住居に対して個人の入居希望者に物件を紹介し、成約に導くことを目的としたサービスです。一方、リーシングはオーナー側の立場に立ち、空室をいかに埋めるかという観点から活動を行います。このように、両者は視点と目的が異なるため、役割も明確に区別されています。
ただし、両者は協力関係にあることも多く、リーシングを行う上では仲介会社が重要なパートナーであることもたしかです。仲介業者はテナント候補を見つけ出す役割を担い、リーシングはその選定から契約交渉、さらには契約更新や解約時の対応まで幅広く関与します。
商業用不動産を安定的に運用するためには、単なる成約数の向上だけでなく、長期的な賃料収入と資産価値の維持が不可欠であることから、リーシングはその要といえるでしょう。
リーシングの具体的な業務内容

リーシング業務には、単なるテナント募集だけではなく、物件の収益性を最大限に高めるための一連のプロセスが含まれています。以下からは、これらのリーシング業務の具体的な内容について詳しく解説します。
賃料設定と市場調査
リーシングは、物件に見合った賃料の設定と市場調査から始まります。
まず、既存テナントの契約内容や業種、稼働状況などを整理し、物件の現在の状況を把握します。次に、近隣エリアにある類似物件の賃料相場や立地、設備などを比較し、競合状況を分析します。
物件ごとの強みや弱みなどの特性を踏まえたうえで、周辺相場とバランスのとれた賃料を設定することで、空室リスクを抑えつつ収益の安定を図ることが可能となります。
テナント誘致と管理業務
賃料と市場の状況が明らかになったら、次に行うのがテナント誘致と管理業務です。
まずは戦略の立案、策定を踏まえオーナーとコンセプトをすり合わせます。次に、物件の特徴や立地条件を踏まえて、どのような業種や企業が対象になるかを検討し、コンセプトを基にテナント候補をリストアップします。
また、テナントとの条件交渉や契約内容の調整などもリーシング業務に含まれており、オーナーに代わって、信頼できるテナントとスムーズな契約締結を目指すことも、このフェーズの目的となります。
募集広告の作成と掲載
テナントを募るためには、物件の魅力をしっかりと伝える広告作成が欠かせません。そのためリーシングでは、物件写真や間取り図、設備情報などを分かりやすく、かつ魅力的に見せる工夫が求められます。
リーシング業者は、プロの視点で見せ方を調整し、不動産ポータルサイトや自社ホームページ、さらには仲介業者のネットワークなど、複数の媒体を通じて情報を発信します。ターゲットとするテナント層にしっかり届くよう、掲載内容やタイミングにも注意が必要です。
情報の精度と見せ方次第で反響が大きく変わるため、専門的なマーケティング戦略が求められます。
仲介会社との連携・内見対応
リーシング業務では、物件の情報発信だけでなく、仲介会社との連携でも重要な役割を担います。
テナント候補が内見を希望した際には、仲介業者と連携しながらスムーズに対応し、現地案内や設備説明などを丁寧に行います。その際、物件の魅力を的確に伝えることで、入居意欲を高める工夫も求められます。内見後の入居申込に対しては、オーナーと調整しながら契約条件を整理し、締結までのサポートを行います。
仲介会社は、テナント候補との最初の接点となる重要な存在であるため、仲介業者との密な情報共有や迅速な対応ができるかが、リーシングの効率や成約率に強く影響します。
オーナーがリーシングを活用するメリット

ここでは、オーナーがリーシングを活用するメリットを解説します。
特に商業用物件の場合、自力で入居者を探すのは難しく、長期間の空室が発生するリスクも高まるため、物件を効率的に運用するためにも、積極的にリーシングを活用するようにしましょう。
空室期間の短縮につながる
賃料収入を得ることによって不動産賃貸事業は成立しますが、空室が続くと、オーナーにとっては収益が生まれないため、できるだけ早期にテナントを確保しなければなりません。そこでリーシングを活用することで、物件に最適なテナントをスピーディーに見つけ出し、 収益性を高めることが可能になります。
リーシング業者は市場動向やエリア特性に詳しく、適正な賃料設定や効果的な広告手法を駆使して、短期間での成約に導いてくれます。さらに、仲介会社との連携をスムーズに行うことで、物件への問い合わせ数も増加し、内見から契約までの流れも効率的になります。
リーシング戦略の立案ができる
物件の収益性を最大限に引き出すためには、単に空室を埋めるだけでなく、長期的な戦略が必要です。
その点、リーシング業者は、入居中テナントの状況やエリアの市場動向を踏まえたうえで、「どのような賃料水準が適切か」「どの層をターゲットにするべきか」「募集のタイミングはいつが最適か」といった要素を総合的に分析し、戦略を立ててくれます。
このような計画に基づいたリーシングを行うことで、物件の価値を維持・向上させながらも収益を最大化することが可能になります。オーナー自身で情報収集や判断を行う手間を省き、プロの視点で物件運用を最適化できる点も大きな魅力です。
適正な入居者を見極められる
リーシングにおいては、入居者を決めるだけではなく、信頼できるテナントを見極めることも重要なポイントです。
リーシング業者は、過去の情報や事業内容、支払い能力などを精査する入居審査を行い、トラブルの可能性が低い入居者を選定するため、家賃滞納や契約違反といったリスクを未然に防ぐことができます。
適切な入居者が決まれば、長期にわたる安定的な賃貸収入が期待でき、オーナーにとっては安心して物件を任せられるようになります。
手間をかけずに集客できる
リーシング業者に業務を委託することで、オーナーは集客に関する一切の手間をかけることなく、効率的にテナント誘致を進めることができます。
具体的には、魅力的な募集広告の作成から、各種不動産ポータルサイトへの出稿、そして多くの仲介業者との連携・やり取りに至るまで、集客に関するあらゆる業務を一任できます。
これにより、オーナーは本業や他の資産運用に集中する時間を確保でき、精神的な負担も大幅に軽減されるでしょう。時間や労力といったコストを削減しながら、プロのノウハウを活用してスムーズな集客を実現できる点が、リーシングの大きな魅力です。
オーナーがリーシングを活用するデメリット
リーシングは物件の稼働率を上げ、収益性を高める有効な手段ですが、一方でいくつかのデメリットも存在します。ここでは、リーシングを活用するこれらのデメリットを詳しく解説します。
管理コストがかかる
リーシング業者に依頼する際には、一定のコストが発生します。具体的にはテナント成約時の仲介手数料や、物件情報を広く告知するための広告費などが必要となります。
これらの費用は物件の規模や立地、募集状況によって異なるため、契約前に予算計画に含めておくことが必要です。また、これらのコストが物件収益に対して過剰である場合、利益を圧迫してしまう可能性もあります。
リーシング業者を効果的に活用するためには、費用対効果を見極めながら運用を行うことが求められます。
戦略次第で成果に差が出る
リーシングは、戦略の立て方によって成果に大きな差が生まれます。
例えば、ターゲット層に合わない賃料設定や魅力が伝わりにくい広告内容が原因でなかなか入居が決まらないこともあります。また、対応のスピードや交渉力も成約率に影響するため、リーシング業者選びは非常に重要です。
実績のあるリーシング業者と連携し、戦略的な計画を立てることで、よりスムーズな空室解消につながります。
情報伝達が不十分な場合がある
リーシング業者と仲介会社との情報共有が不十分な場合、写真や間取り、立地条件といった基本情報の不足だけでなく、周辺環境や物件の強みなどが適切にアピールされないケースもあります。
このような事態を避けるためには、リーシング業者が仲介会社との間で適切にコミュニケーションを取り合い、情報の更新や確認作業を丁寧に行うことが重要です。
リーシングを依頼する際の注意点・コツ
リーシングを業者に依頼する際には、事前の見極めが非常に重要です。
まず確認すべきは、その会社の過去の実績です。特に、自身が所有する物件と類似した物件の取り扱いや、同じエリアでのリーシング経験が豊富かどうかをチェックしましょう。地域性や物件の特性を理解している業者であれば、より的確な賃料設定やターゲット選定が可能となり、早期のテナント誘致が期待できます。
また、実績の中でも、空室をどれだけ短期間で埋めたか、どのようなテナントを誘致しているかなども確認材料となります。さらに、対応の丁寧さや報告の頻度、契約後のフォロー体制なども含めて比較検討することで、信頼できるパートナーを選ぶことができるでしょう。
リーシングに関するよくある質問

最後に、リーシングに関するよくある質問と、その答えをまとめました。特に初めてリーシングを依頼する場合には、不明なことは遠慮なく担当者に質問するようにしましょう。また、必要に応じて複数の業者に相談することもおすすめします。
リーシングを自社で行うことはできますか?
リーシング業務をオーナー会社自身で行うことは可能です。
ただし、リーシング業務には物件の魅力を効果的に発信するノウハウや、テナントとの交渉力、不動産市場に関連する知識や地域ごとの賃料相場に関する理解が必要になります。また、仲介会社やポータルサイトとのネットワークも必要になるため、初めての方や副業として不動産投資を行っている方にとっては負担が大きくなります。
こうした理由から、多くのオーナーはリーシング業者に業務を依頼しています。それにより、効率的な募集活動や的確なテナント選定が期待でき、結果として空室期間の短縮と収益性の向上と、オーナー会社の負担軽減につながります。
リーシングを依頼する費用はどのくらい?
リーシングを業者に依頼する場合の費用は、一般的に成約した賃料の1〜2ヵ月分が相場となっています。費用には賃料だけでなく、共益費や駐車場代といった固定費が含まれる場合もあるため、契約前にしっかりと内訳を確認することが大切です。
また、物件によっては最低料金が設定されていることもあり、成約賃料が低めの物件では割高に感じるケースもあります。業者ごとに料金体系が異なるため、複数社から見積もりを取り、サービス内容と費用のバランスを比較することが失敗を防ぐポイントです。その際には、コストだけでなく、どこまでサポートしてくれるかも確認しておきましょう。
| manabu不動産投資に会員登録することで、下の3つの特典を受け取ることができます。 ① ウェビナー案内メールが届く ② オススメコラムのお知らせが届く ③ クリップしてまとめ読みができる |
- コラムに関する注意事項 -
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。
当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。
外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。