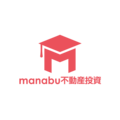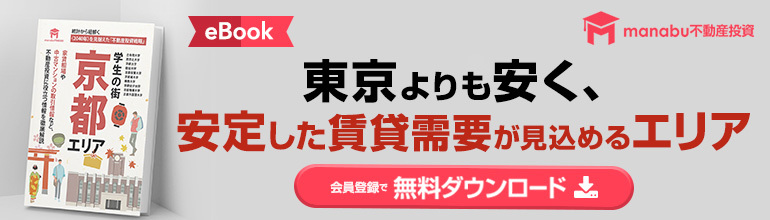私道は公共の用に供される公共物である一方で、土地所有者の所有物でもあるため、所有者がさまざまな負担を受けなければなりません。そのため不動産投資の観点からは「私道負担のある土地はやめとけ」と評価されることもあります。
本コラムでは、私道負担の意義や固定資産税の扱い、メリット・デメリットのほか、私道負担のある土地を購入する際の注意点を具体的に解説します。
私道負担とは?

私道負担とは、所有している土地の一部が私道となっており、公共の通行のための義務や制限が生じることを指します。国や各自治体が所有する道路を公道といい、それ以外の個人や団体が所有する道路を私道といいます。
そもそも建築基準法において建物が建てられる土地とは、「幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」と定められています。これは「接道義務」といい、災害時や緊急時に車が通れる道を確保することが目的とされています。私道負担の多くは、敷地の一部を私道として扱うことで、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接する「接道義務」を果たすために用いられています。
道路は、基本的に所有者の自由な管理のもとに置かれますが、私道については一定の条件を満たすと公的なルールの影響を受けることになります。
例えば、私道であっても不特定多数の人が日常的に利用している場合、行政から「公衆用道路」と認定されることがあります。この場合、所有者であっても道路を封鎖したり、通行を制限したりすることはできません。また、一般の公道と同様に維持管理の義務が生じる可能性もあります。
さらに、私道が建築基準法における「道路」として認められている場合、建築計画にも影響を及ぼすことがあります。特に、建物を建て替える際には、セットバックと呼ばれる道路後退義務が発生するケースがあるため、私道の位置や幅員について事前に確認することが重要です。
私道負担とセットバックの違い
セットバックとは、建築基準法で定められた幅員(4mまたは6m)を満たさない道路に土地が接している場合に、道路の中心線から一定の距離だけ敷地を後退させ、道路幅員を確保しなければならないことを指します。セットバックの目的は、将来的な道路の拡幅を見据えた措置であり、建物の密集を防ぎ、防災性を高めることにあります。
注意点として、建築基準法は、公道だけでなく私道にも適用される場合があります。例えば、土地に面している唯一の道路が私道で、その幅員が4mに満たない場合には、私道であってもセットバックが必要になることがあります。この場合、私道負担とセットバックの両方の負担を負うことになり、敷地がさらに狭くなってしまう可能性があります。
私道負担とセットバックはそれぞれ異なる概念ですが、土地の利用に大きな影響を与えるという点では共通しています。道路に面している土地を購入する際には、私道負担の有無だけでなく、セットバックに関する情報も十分に確認することが大切です。
セットバックに関する概要や注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。
【関連記事】セットバックとは?発生する理由や必要費用・購入してよいケースを解説
私道負担の固定資産税はどうなる
私道は個人の所有物であるため、固定資産税および都市計画税の課税対象となり、原則として所有者が納税義務を負います。共有持分となっている場合には各自が持分に応じて納税義務を負います。さらに、宅地と同様に私道を取得する際には不動産取得税や登録免許税、都市計画法の市街化区域内に指定されている場合は都市計画税、相続した場合には相続税も支払う必要があります。
ただし、自治体によっては、私道であっても各自治体に申請し「公衆用道路」として認められた場合、固定資産税・都市計画税・不動産取得税が非課税となる措置が取られることがあります。「公衆用道路」とは、一般公衆の交通のために利用されている道路のことをいいます。公衆用道路として認定されるためには、道路が広く一般の通行に供されていることが条件となるため、事前に自治体の窓口で確認することが重要です。
また、私道が含まれる土地を購入する際には、登記簿謄本の地目が「宅地」ではなく「公衆用道路」となっているかを確認するようにしましょう。加えて、売主の納税通知書を確認し、該当する地番が「非課税」となっているかどうかもチェックすることも重要です。
これらの事前確認を怠ると、購入後に予期せぬ税負担が発生する可能性があるため、弁護士や税理士などの専門家にも確認を依頼するなど、慎重な判断が必要です。
私道負担のデメリット・注意点

以下からは、私道負担を抱えるデメリットや注意点を解説します。私道を含む土地を購入する際には、これらのデメリットをしっかりと把握し、事前に対策を講じておくことが重要です。
敷地の利用が制限される
私道が敷地内に含まれる場合、土地の利用に一定の制限がかかることがあります。例えば、私道上に建築物を建てたり、門扉や駐車場の設置も制限されたりします。さらに、私道部分が建築不可部分となることで、建築可能部分の建ぺい率や容積率の計算にも影響を及ぼします。
その結果、想定していた建築プランを実現できない可能性や、土地の市場価値が下がってしまうこともあります。
道路の管理を負担しなければならない場合もある
私道は公共の用に供されている場合であっても、所有権自体は個人にあるため、所有者には維持管理の責任が発生します。具体的には、道路の舗装が劣化した場合の補修や、上下水道などインフラの維持も、所有者の負担となります。また、道路上に放置されたゴミの処分や、違法駐車の対処も求められることがあります。
これらの管理を怠ると、道路の状態が悪化し、通行人の転倒や事故の原因となる可能性があります。その結果、所有者が賠償責任を負うリスクも生じるため、定期的な点検と適切な維持管理が欠かせません。なお、自治体によっては私道の舗装工事などに対する助成制度を設けている場合があるため、整備課などの窓口に相談することも有効です。
他の共有者とトラブルになることがある
私道を複数の所有者で共有している場合、維持管理や修繕の際にトラブルが発生することがあります。例えば、道路の補修工事を行う際には、共有者全員の同意が必要となるため、意見が合わずに工事が進まないケースが考えられます。また、私道を掘削してガス管や水道管を敷設する場合にも、共有者全員の許可が求められることがあります。
このようなトラブルを防ぐためには、事前に「掘削承諾書」などの書類を交わし、私道の管理に関するルールを明確にしておくことが重要です。共有者との良好な関係を維持し、円滑な管理体制を整えることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、固定資産税の納税通知書は代表者に送付され、その代表者が他の共有者から持分に応じた負担分を回収して納税することになります。そのため、トラブルを防ぐためにも、当事者間でどのような流れで清算を行うかの取り決めを事前にしておくなどの注意が必要です。
私道負担にはメリットも
私道負担にはデメリットがある一方で、不動産投資の観点からも注目すべきメリットもあります。以下からは、私道負担に関する主なメリットを3つ紹介します。
相場よりも安く購入できることが多い
私道負担がある土地は、一般的な土地と比べて利用に制限がかかるため、価格を抑えられる傾向にあります。そのため予算を抑えて土地を購入したい人にとって、私道負担のある土地を購入することは大きなメリットとなるでしょう。
また、価格が安い分、建築コストやリフォーム費用に予算を回せるという利点もあります。特に土地購入と建築費用をトータルで考える場合、私道負担のある土地を選ぶことで、コストを最適化できる可能性があります。
交通量が少なく静か
私道は公道と異なり、一般の車両が頻繁に通行することが少ないため、比較的静かな環境を期待できます。騒音や振動の影響が少なく、落ち着いた住環境を実現できることから、特に子育て世帯や静かな生活を求める人にとっては大きなメリットとなるでしょう。
また、私道は通行する車両のスピードも抑えられることが多いため、安全性が高いという特徴もあります。車庫入れの際にも、急いで動く必要がなく、ゆっくりと落ち着いて操作できるのも利点の一つです。
私道部分も含めて売却益が得られる
私道負担のある土地を売却する際には、所有者の権利によって私道部分も含めて売却することが可能です。私道とだけ接している土地については、私道とセットになってはじめて土地の価格を正当に評価できるため、私道部分も含めた売却益を得ることになります。
私道負担の土地・物件を購入する際に確認すべきポイント
私道負担のある土地や物件を購入する際には、予期せぬトラブルや出費を回避するため、事前に確認すべきポイントが多くあります。実際に購入を検討する際には、以下に紹介するポイントをしっかり確認しましょう。
私道の利用状況を確認する
私道を含む土地を購入する際には、その利用状況を細かく確認することが大切です。特に、道路の補修状況や管理体制について把握するようにしましょう。もし舗装が傷んでいたり、排水が適切に行われていなかったりする場合には、将来的に補修工事の費用がかかる可能性があります。
また、近隣住民による私道の不正使用があると、購入後にトラブルに発展することがあるため、不法投棄や不法占拠がないかも重要なチェックポイントとなります。特に、購入後に近隣住民となる相手だと、のちのち注意しづらくなることも考えられるため、慎重に確認することが求められます。
私道の権利状況を確認する
購入に先立ち、私道の権利関係がどのようになっているのかを確認することも重要です。具体的には私道が単独所有なのか、それとも複数の所有者による共有物なのかを調査しましょう。
特に、所有者が複数の場合や、相続の影響で登記簿に所有者の変更が反映されていない場合には、手続きが複雑になることが考えられます。さらに、共有している私道全体を売却したい場合は共有者全員の同意が必要になるため、今後の取引がスムーズにいかない可能性もあります。
そのため、購入前に私道部分の登記簿を確認し、権利関係を整理しておくことが大切です。共有者がいる場合には、他の所有者にヒアリングするのもおすすめです。
私道の通行掘削権を確認する
私道に接する土地では、ライフラインの整備が課題となることもあります。例えば、上下水道・ガスなどが私道部分を経由している場合には、私道の掘削工事が必要となるため、工事にあたっては所有者から掘削工事の許可を得なければなりません。
そのため、土地の所有者が私道部分の通行掘削権を有しているのかを確認し、これを譲渡できるのか、譲渡できない場合にはどのように権利を取得できるのかなど、慎重に確認する必要があります。
私道負担でよくある疑問

最後に、私道負担に関するよくある疑問と答えをまとめました。
私道負担がある土地に建物を建てることはできる?
私道負担がある土地に建物を建てることは可能ですが、いくつかの制約があります。前述した通り建築基準法では、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります。私道負担部分は建築面積には含まれないため、実際に建物を建てられるのは、私道を除いた部分のみとなります。
また、私道が建築基準法第42条2項に該当する「2項道路」である場合、道路幅員を確保するためにセットバックが求められることがあります。セットバックにより、さらに利用可能な敷地面積が減少する可能性があるため、事前に確認が必要になります。
私道負担部分にフェンスや塀を設置してもいい?
原則として、私道負担部分にフェンスや塀を設置することはできません。私道負担部分は公共の通行のために確保されているため、所有者であっても自由に利用することは制限されます。
万が一、通行を妨げるような構造物を設置した場合、近隣住民とのトラブルにつながる可能性があります。また、行政によって撤去を求められるケースもあります。
私道負担がある土地を購入すべきか迷ったときは?
私道負担がある土地を購入するかどうかを判断する際には、私道の所有者や通行権の有無、維持管理のルールなどを確認することが重要です。特に、第三者の通行権が認められているかどうか、修繕費用の負担がどのように決められているかを明確にする必要があります。
これらの点が曖昧な場合、後々トラブルに発展する可能性があります。もし自分自身で判断が難しい場合は、不動産会社や弁護士などの専門家に相談し、法的リスクや維持費用の見通しについて助言を受けることをおすすめします。
| manabu不動産投資に会員登録することで、下の3つの特典を受け取ることができます。 ① ウェビナー案内メールが届く ② オススメコラムのお知らせが届く ③ クリップしてまとめ読みができる |
- コラムに関する注意事項 -
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。
当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。
外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。